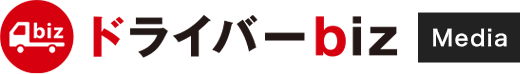最近、街でも目にする機会が増えてきた「介護(福祉)タクシー」。
これは、体の不自由な人……つまり“要介護者”が利用しやすいように工夫されたタクシーのことを言います。
超高齢化社会に突入した日本では、介護を必要としている人が増加しており、「介護タクシー」およびその「ドライバー」の存在が必要不可欠なものとなっています。
前回の記事では、この「介護タクシーのドライバーになる方法・必要な資格について」のご紹介をさせていただきました。
今回は、「介護タクシードライバーの給与・やりがい・将来性」について、詳しくお話をしていきたいと思います。
「介護タクシードライバー」の給与や収入について
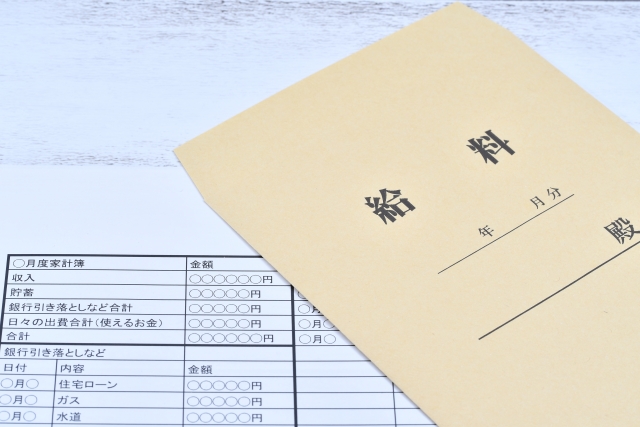
まず、介護タクシーのドライバーとして働く方法は、以下の2種類が存在します。
②個人で介護タクシー事業を開業する
個人で介護タクシー事業を開業するには一定の条件を必要とするため、いきなり開業することは難しいです。
(詳細は、前回の記事にて)
そのため、まずは①の「介護タクシー事業を行っているタクシー会社に就職する」ことが基本となってくるかと思います。
そして、上記に就職するとして、募集している「雇用形態」は、企業によって異なることとなります。
◆パート・アルバイト
◆契約社員 など
基本は「正社員」か「パート・アルバイト」かのどちらかになることがほとんどですが、この2つだけでも給与額は大きく変動します。
当サイトでは、以下のような求人サイトも取り扱っております。
これに掲載されているデータをもとに平均給与を算出してみると、以下のようになりました。
≪月給≫
◆上限平均:250,000円ほど
◆下限平均:180,000円ほど
≪年収≫
◆上限平均:3,550,000円ほど
◆下限平均:2,590,000円ほど
「パート・アルバイトの時給」
◆上限平均:1,100円ほど
◆下限平均:1,000円ほど
上記は“平均給与”のみの金額となるため、残業手当や賞与など、月によって変動する金額は含まれていません。
また、あくまで“平均”であるため、勤務する事業所によって、金額は大なり小なり変動するかと思います。
加えて、上記は“手取り金”ではないため、ここから税金や諸経費などが差し引かれることにもなります。
この点を考慮し、参考程度にとどめておくようにしてください。
なんにせよ、手取りで見ると、正社員の給与の場合は「平均20万前後」となることが多いかと思います。
そのため、「この仕事だけで生活を賄っていくor家族を養っていく」となると、少々厳しい点もあるかもしれません。
「介護タクシードライバー」は、未経験からでも応募できる?
必須となる資格とは?

まず、介護タクシードライバーになるためには、必須となる資格が2点あります。
それが、以下です。
②介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)
特に「タクシーの移動(送迎)業務」が仕事の基本となるため、①は絶対に必須であり、取得していなければ応募をすることはほぼ不可能です。
ただし、②については、就業後に取得できる企業もあります。
資格取得支援として、試験代を会社側が負担してくれることもありますので、この点が気になる方は求人募集の「応募資格」や「待遇」などの項目を確認してみてください。
とはいえ、上記2つの資格を就業前にどちらも取得しておけば、選考の時点で有利になることは間違いありません。
また、「介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)」以上を取得しておけば、「介護職員」として働けるという選択肢も増えてきます。
取得しておいて損はないので、「介護タクシーor介護関連の仕事に興味がある」という人は、ぜひ資格取得に向けて行動してみてください。
“未経験”でも応募はできる?
結論から言うと、「介護タクシー業務・介護業界での経験がない人(=未経験)でも、求人募集をしている企業はたくさん存在する」です。
ただし、上記で挙げた資格は必須としている企業がほとんどです(特に普通自動車二種免許は絶対である)。
そのため、資格さえ取得しておけば、未経験でも介護タクシーの職に就くことは十分可能です。
もちろん、資格と同じく「介護職の経験がある人」の方が歓迎・優遇されることもあります。
気になる方は、求人募集を細かくチェックして、分からないことがあれば、企業側に質問してみるといいでしょう。
「介護タクシードライバー」のやりがい・大変なことについて
やりがい
一般のタクシーの場合、基本的には同じ人を何度も送迎することは稀です。
しかし、介護タクシーは“予約制”であり、ケアマネージャーや介護施設から“紹介”されることもあって、同じ人物を送迎することが多くなります。
例えば、以下のような場合です。
◆「通学」のため、(同じ人物を)特別支援学校などに送迎する
そのため、「利用者さんとの関係性を作りながら仕事ができる」というメリットがあります。
時には、利用者さんから感謝の言葉を伝えられ、そこにやりがいを感じる方もいらっしゃいます。
介護タクシードライバーは、営業による新規開拓ももちろん必要となります。
そしてそれと同じく、仕事を紹介してくれるケアマネージャーや利用者さんもいらっしゃるのです。
そういう人たちとしっかりとして関係性(信頼関係)ができてくると、ある程度“自分のペースで仕事ができる”ようにもなります。
加えて、この仕事は「独立開業」することも可能です。
一定の条件こそ必要にはなりますが(詳細は前回の記事にて)、上記のように多くの方々との関係性(信頼関係)をつくることができれば、開業してさらに自分のペースで仕事ができるようにもなるかと思います。
もちろん、仕事がうまく回せるようになれば、タクシー会社で働いていた時よりも収入は大幅に増加することにもなるでしょう。
自分のペースを掴むまでは大変かもしれませんが、自分のペースを掴めるようになれば、取り組みやすい仕事と言えるかもしれません。
大変なこと
介護タクシーを利用する人は、基本的に「介護保険」を利用されます。
そして、介護タクシーで介護保険を適用可能にするためには、以下の3つの条件をすべてクリアする必要があるのです。
◆一人で公共交通機関を利用できない
◆家族や友人など、付き添う人がいない
つまり、介護タクシー利用中は「ドライバーと要介護者の1対1の状況となる」となります。
(一部、条件次第で付き添い人が同乗することはある)
ある程度、利用者さんと関係性が作れてくれば大丈夫ですが、最初のうちはコミュニケーションを取ることも大変となる場合もあるかもしれません。
また、介護タクシードライバーの業務の一つに、「介助」も必須となります。
介助内容は同じであっても、介助方法は利用者によって千差万別です。
特に、業務になれるまでの間は、この点にも「大変だ……」と感じる人もいるかもしれません。
介護タクシードライバーの将来性について
将来性も認知度も十分にある

こちらも結論から言うと、「介護タクシーの需要は今後も増え続ける」ということと「その認知度は、どんどん上昇している」ということです。
介護タクシーの利用者は、介護を必要とする人が対象であるため、高齢者や障がいを持つ人などさまざまな人が利用します。
送迎だけでなく、身体介護もしてくれる介護タクシーの存在は、こういった利用者やそのご家族にとって非常にありがたい存在なのです。
そのため、今後も「介護タクシー」というものがなくなることはありません。
また、冒頭でもお伝えしたように、現在の日本は「超高齢化社会」に突入しており、今後も高齢者の割合はどんどん増えていきます。
それに伴い、介護が必要な方も増えるため、必然的に介護タクシーを利用する人も増加していくと言えるのです。
また、都心部では車を保持していない人も増えているため、移動に介護タクシーを利用する人も増えてきています。
このことから、認知度もどんどん上昇しており、利用者も年々増加していくものと考えられています。
働き方も選択できる
上項でもお伝えした通り、介護タクシーの仕事に就くには「普通自動車二種免許」と「介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)」が必須となります。
そのため、ドライバーとしての仕事だけでなく「介護職員」として勤務できる可能性も高いのです。
また、介護タクシーだけでなく、デイサービスなどの送迎ドライバーとしても働くことができます。
高齢者の増加にともない、デイサービスの利用者も増加しています。
そのため、介護タクシードライバーの需要はますます高まっていると言えるのです。
もちろん、介護タクシーとして独立開業する道もあります。
働き方はある程度選択することができるので、この仕事に関心がある方は、知見を広げてその一歩を踏み出してみるのもいいかもしれません。
まとめ
以上が、「介護タクシードライバーの給与・やりがい・将来性について」のご紹介となります。
介護業界は、基本的に給与額が低くなっており、それは介護タクシードライバーであっても同様のことが言えます。
ただし、勤務する事業所によって給与・手当・待遇などは変動します。
「良い条件の事業所で勤務がしたい」という場合は、いろいろな求人情報を検索して、自分に合った求人に募集をかけてみるといいでしょう。
また、この仕事は将来性・認知度・働き方の選択など、今後の可能性も十分にあります。
資格こそ必要ではありますが、その資格も比較的取得難度は易しいため、誰にでも(勉強さえすれば)取得できるはずです。
加えて、現代は「仕事の大半が機械にとって代わられる」という現象が起きています。
しかし、「送迎」「介助」の両点を行えるのは、人間だけです。
そのため、この仕事が機械にとって代わられるということは、将来的にも早々起きることはないかと思います。
将来性も十分にありますので、関心がある方は、ぜひ知見を広げて、その一歩を踏み出してみてください。
「年齢」「学歴」「経験」などが不問であることも多い職種のため、誰にでもチャンスのある仕事ではないかと思われます。