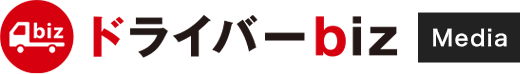インターネットの普及でネット通販やオンラインショップの利用者増加により、宅配業者の存在にも需要が高まっています。
宅配業者として働くには会社に勤務する選択肢が大半を占めると思いますが個人事業主として開業するという道も実は存在しているのです。
個人と法人では立場や状況が大きく異なるため、同じ業務でも向き不向きが発生することでしょう。
そこで、運送業の個人事業主になるための方法や、仕事をする上でのメリットデメリットを解説いたします。
個人で運送業を始める方法は?

前述したように個人で運送業を開業することができます。
しかし、個人で開業するにはいくつか注意が必要です。
個人事業主として運送業開業は可能ですが、白ナンバーでの運送業が許可されたわけではありません。
「貨物自働車運送事業」に利用される車両は
・白
・緑
・黒
の三つに区分されており、その中でも白ナンバーはタクシー等と同様、金銭をもらって運送業を経営することはできません。
しかし、運送、運搬に金銭を要求せず、自身の会社の商品や加工先の工場など、日常的なやり取りの範囲内であれば運送業の許可は必要ありません。
もし、白ナンバートラックで運送し、運賃を受け取っているのであれば「運送業許可」をもらう必要があります。
運送業を開始するための許可申請条件

運送業は法人のイメージが強いと思いますが、きちんと条件さえ満たせば個人でも特に問題なく開業することができます。
その条件とは以下の運輸業の許可申請を行うことです。
一般貨物自動車運送事業
軽トラックを除く、5両以上の車両と5名以上のドライバー、1名以上の運行管理資格者と整備管理者が必要です。
他にも事務所や駐車場など、細かな条件があり、申請が通るまで3~4か月ほどかかってしまいます。
貨物軽自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業に比べてやや軽い条件になります。
車両は1台以上、軽トラックまたは125㏄以上の自動二輪車でも問題がなく、整備管理者も不要で、ドライバーと運行管理資格者は1名以上のため自分だけでの開業が可能です。
申請も即日で完了するので自身一人で開業するなら「貨物自動車運送事業」がおすすめです。
個人で運送業をする上での留意点

個人事業だと法人と違い、どうしても知名度が低くなってしまうため、仕事のほうからやってくる機会はかなり稀でしょう。
開業したものの、思い付きだけで行動したり、問題を前に解決策を考えずにいたりすると自己破産しかねませんので、しっかりと計画を練って開業しましょう。
個人事業でも人の確保が必要
個人事業と聞くと「一人で仕事する」というイメージが強く従業員を雇わなくても問題がないと思われがちですが、その考えには注意が必要です。
一般貨物自動車運送事業
軽トラックを除く、5両以上の車両と5名以上のドライバー、1名以上の運行管理資格者と整備管理者が必要です。
他にも事務所や駐車場など、細かな条件があり、申請が通るまで3~4か月ほどかかってしまいます。
「運送業を開始するための許可申請条件」にて紹介したように、運送業を開業する際に必要な運送業許可の中には、個人事業主である自身を含めて最低でもあと5人の人材を確保しなければ申請が下りないものもあります。
営業必須
個人で運送業許可取得を考えている方の多くは、今現在お付き合いがあり、仕事の受注の見込みがあるため一定の売り上げは確保されている状況にあると思います。
しかし、そこで満足したままでは危険です。
もし現在確保されているお付き合いのある方から、万が一仕事がもらえなくなってしまった場合、他の荷主を探さなくては事業継続が危うくなってしまうからです。
営業活動はビジネスをやるうえで避けては通れない必須事項ですので、法人であれ個人であれ、もしもの時に困らないように身に付けておいて損はないでしょう。
他社との違いが求められる
お付き合いのある方相手であれば、自身の会社が法人であれ、個人であれあまり気には留めないでしょう。
しかし、自身を全く知らない新規のお客さんを相手にする場合には、個人であるより法人であったほうが圧倒的に有利になることが多いのが現状です。
法人であることのほうが社会的信用が大きいため、個人が対抗するには他社に比べて自社に依頼したほうがメリットがあるとお客さんに感じてもらい、他の運送会社との明確な違いを見出してください。
その違いに気づいてもらえると、運送業でなくとも多くのお客さんから選ばれる事業者になるでしょう。
運送業の個人事業主になるメリット・デメリット
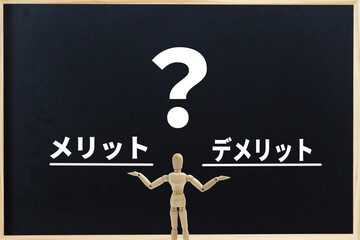
メリット
自分のペースで勤務可能
勤務時間、勤務地にとらわれず、自由な働き方ができるため、休日の取り方、就業時間に始業時間も自身の好きなように決められるのは個人事業ならではの大きなメリットの一つです。
人間関係の煩わしさも会社勤めに比べて大幅に少なくなりますし、育児や介護の合間の空き時間に仕事ができることもあり、運送業を開業する女性も増えています。

開業のハードルは低め
軽貨物運送業以外の運送業である『一般貨物自動車運送事業』や『特定貨物自動車運送事業』は許可制のため、条件をクリアする必要があったり、申請が通るまで3~4か月待たなければいけなかったり、届け出たら即開業できるわけではありません。
しかし、軽貨物運送業は届け出たらすぐに開業が可能なため、その開業のハードルの低さが魅力です。
また、普通免許と軽貨物車、車庫の準備ができれば開業可能なので、店舗を用意する必要もなく、開業のための費用も少なめで済みます。
頑張りしだいで収入を増やすことができる
収入は出来高制のため、技術を身に付けるまでは苦労を要するかもしれませんが、経験を積み、事業拡大を目指せば法人化できる可能性も大いにあるのが魅力です。
自身の成長とお客さんの笑顔のためにも、高い目標を掲げながら業務に励めることはとても良いことです。
デメリット
法人よりも社会的信用度が低い
・節税対策が取りにくい
・銀行の融資が受けにくい
・新規のお客さんが取りずらい
大きな会社に比べて知名度も低く、会社の一員でないことでどうしても法人と比べると社会的信用度が低くなってしまいます。
自己負担が大きい
車両の維持費、保険、年金など会社が持ってくれていたものを自身が負担しなければならなくなるため、会社員に比べて自己負担金額が多いです。
ケガや病気で休まざる負えなくなった場合にも休養中は一切収入が発生しなくなってしまいます。
手続きが面倒(多い)
従業員を雇わない場合、開業のための申請や準備、手続き、確定申告に車両設備費用、保険料、営業活動など…すべて自身一人で行わなければならないためとても大変です。
まとめ
いかがだったでしょうか?
個人事業主というとフリーランスと混合してしまう方も多いかと思いますが、単身で事業を行うだけでなく人を雇用することもできます。
運送業の経験があり、資金さえ調達できるのであれば運送業での開業はそう難しいことではありません。
もちろん楽なことばかりではありませんが、法人という強いライバルがいる中、お客さんに個人として仕事を任せてもらえた時、きっととても大きな達成感と成長を感じることができるでしょう。
この記事が個人で運送業を始めたいと思っている方たちに、少しでも参考になれれば幸いです。